

太陽工業コラム

テント倉庫は、骨組みにシート(テント生地)を張ることで完成する建築物であり、短期間かつ低コストでの建設が可能です。
しかし、建物の一種である以上、建築基準法や消防法などの法律を遵守する必要があります。
特に消防法では、テント倉庫の規模や用途によって求められる消防設備が異なるため、適切な設備を備えることが不可欠です。
本記事では、消防法に基づき必要な設備の条件や、消防対策として重要なテント生地に関する情報まで詳しく解説します。
消防法とは?

消防法は、火災の予防や被害の最小化を目的とした法律です。
人命や財産を守るため、火災の予防措置、設備の設置、訓練の実施、点検の義務などが規定されています。
この法律は、すべての建物に適用され、違反すると厳しい罰則が科される場合があります。
具体的には、火災の発生を防ぐため、防火管理者の選任や消防計画の作成が義務付けられています。
また、従業員や住人を対象にした避難訓練の実施も求められています。これにより、実際の火災発生時に迅速な対応ができるようになります。
さらに、建物には消防設備の設置が義務付けられています。スプリンクラーや消火器、火災警報器などの設置が必要であり、定期的な点検と整備が求められます。
これを怠ると、安全性が損なわれるだけでなく、法人に対し最高1億円の罰金が科されることがあります。
避難経路の確保も重要です。非常口の標識設置や通路の確保が義務付けられており、非常時の混乱を防ぐための措置が求められています。
消防法に違反した結果、火災による被害を拡大させた場合、企業や管理者は重大な社会的責任を問われる可能性があります。
この法律は、社会状況に応じて改正が行われています。
例えば、2001年に東京都新宿区歌舞伎町で発生した火災を受け、防火管理の強化が行われました。このような過去の事故を教訓に、法改正が進められています。
消防法がテント倉庫に義務付ける消防設備とは?

テント倉庫における消防設備の設置は、消防法に基づき義務付けられています。
これは火災発生時の迅速な対応を目的とした規定であり、延べ床面積に応じて必要な設備が異なります。
具体的には、延べ床面積が500㎡未満の場合、消火器の設置が求められます。
500㎡以上700㎡以下では、消火器に加え、火災報知器の設置が義務付けられます。
さらに、700㎡を超える場合は、消火器と火災報知器に加え、屋内消火栓の設置が必要となります。
なお、これらの規定は、不燃性の物品を保管する倉庫であっても例外なく適用されるため、適切な設備設置と維持管理が重要です。
消防法の基準を満たし、安全な倉庫運営を行うことが求められます。
消防法に基づく、テント倉庫に必要な消火器について

テント倉庫に消防用設備を設置する際には、消防法に基づく必要があります。
特に消火器については、設置場所や個数に関して明確な規定が定められています。
そのため、テント倉庫の規模や用途に応じた基準を事前に確認し、適切に配置することが求められます。
必要な消火器の数
消防法に基づき、テント倉庫に適切な消火器を設置するためには、「能力単位」という指標が重要となります。
能力単位は、消火器が持つ消火能力を示し、消火薬剤の種類やサイズによって異なります。
例えば、粉末3型消火器の能力単位は1、粉末6型消火器の能力単位は2となります。
必要な消火器の数を決定するには、倉庫の延べ面積と1単位あたりの適用面積に基づいて計算を行います。
計算式は「延べ面積 ÷ 1単位/m² = 能力単位」となります。
この1単位/m²の基準は建物の構造によって異なります。
耐火構造の建物では1単位あたり200㎡、非耐火構造の場合は100㎡が基準となります。
例えば、耐火構造のテント倉庫で延べ床面積が1000㎡の場合、「1000㎡ ÷ 200㎡ = 5」となり、必要な能力単位は5です。
この能力単位5を満たすためには、粉末3型消火器を5本設置するか、能力単位が2の粉末6型消火器を3本(合計6単位)設置することで対応できます。
倉庫の延べ面積や建物の構造を考慮し、必要な能力単位を算出した上で、適切な種類と本数の消火器を配置することが求められます。
消防法の基準を確認し、必要な能力単位を満たす配置を行いましょう。
消火器設置の基準
テント倉庫における消火器設置の基準は、防火対象施設の安全確保を目的に詳細に規定されています。
設置基準として、各フロアに消火器を備え、あらゆる部分からの歩行距離が原則20m以内、大型の施設では30m以内で利用可能であることが求められます。
また、迅速な使用が可能となるよう、通行や避難の妨げにならない場所に設置し、緊急時にもすぐ携行できることが重要です。
さらに、消火器は床面から1.5m以下の位置に取り付ける必要があり、屋外や厨房、蒸気・ガスが発生する箇所では格納箱に収納して保護しなければなりません。
また、指定可燃物を貯蔵する施設や多量の火気を使用する場所では火災リスクが高いため、消火器の設置基準も厳格になります。
特に、綿花類や木材、わらなどの指定可燃物を扱う場合、それらの量に応じて、指定数量の50倍の消火器を設置することが義務付けられています。
さらに、市町村の火災予防条例によって、特定の施設には追加の要求が適用されるケースもあるため、地域ごとの条例内容を把握し、適切に対応することが重要です。
テント倉庫の消防対策に役に立つ消防用設備

テント倉庫では、消防法で求められる最低限の消防用設備を設置する必要があります。
これは、火災時の安全確保に欠かせません。さらに、より高い安全性を確保するためには、倉庫の規模や用途に応じて、他の消防用設備の設置も検討すべきです。
例えば、火災を早期に検知できる自動火災報知設備や、迅速に消火を行えるスプリンクラー設備などが挙げられます。
これらを適切に導入することで、火災リスクを最小限に抑え、安全な倉庫運用が可能になります。
消火設備
消火設備とは、火災の予防や制御、消火を目的として設置される設備のことを指します。
代表的なものとして、屋内外の消火栓やスプリンクラー、水蒸気消火設備、消火器などが挙げられます。
火災発生時にこれらを迅速に使用することで、適切な初期対応が可能となり、被害の拡大を防ぐことができます。
特に、スプリンクラーや消火栓は延焼を抑制し、大規模な被害を防ぐ重要な役割を果たします。
警報設備
テント倉庫における消防対策として重要なのが警報設備です。
これは火災の発生を早期に感知し、警報を発するための設備全般を指します。
その中には火災報知器や非常放送設備が含まれており、火災発生時に即座に通知を行います。
さらに、自動火災報知機やガス漏れ警報機、漏電火災警報器なども重要です。
これらは建物内にいる人々へ緊急事態を知らせるだけでなく、迅速に消防機関へ通報する役割を担っています。
近年では、空気中の環境変化を検知し火災リスクを予測するシステムの導入が進んでおり、電気火災やその他の潜在的な危険を未然に防ぐことが可能になっています。
避難設備
避難設備は、火災が発生した際に安全に避難するために使用される重要な器具です。
具体的には、非常用照明や誘導灯、避難はしごなどが設置されます。
特に、2階以上の建築物では、救助袋や避難すべり台も適用され、迅速な避難が可能となります。
これらの設備は、火災時における安全な避難を確保するために不可欠であり、人命を守る重要な役割を果たします。
消防用設備に重要な定期点検

消防用設備は、火災などの非常時に確実に作動することが求められます。
そのため、定期的な点検と報告が法律で義務付けられています。
点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。
「機器点検」は、設備の外観を確認したり簡単な操作を行ったりする点検です。
これは6ヶ月に1回実施され、設備の基本的な状態を維持するために欠かせません。
一方、「総合点検」は、実際に設備を作動させ、機能が正常に働くかを詳細に確認する点検です。
こちらは1年に1回の実施が必要とされています。
これらの点検は、消防設備士や専門資格を持つ技術者によって行われることが原則とされています。
また、点検後の結果は所轄の消防長または消防署長へ報告が求められます。
報告頻度は、特定防火対象物(商業施設など)では1年に1回、非特定防火対象物(倉庫など)では3年に1回です。
点検報告を怠ると、点検報告義務違反となり、30万円以下の罰金や拘留の対象となる可能性があります。
法的リスクを避け、火災時の安全を確保するためにも、定期点検と適切な報告を徹底することが重要です。
テント倉庫の消防に重要なテント生地について

テント倉庫の防火対策では、消防法に準じた設備の設置が求められます。
しかし、それだけでなく使用されるテント生地の選定も重要です。
テント生地は、「不燃生地」か「防炎生地」のどちらを使用する必要があります。
不燃生地と防炎生地の特性を理解し、適切なものを選ぶことが火災リスクを低減するために欠かせません。
まずはそれぞれについて詳しく解説します。
不燃生地
不燃生地とは、建築基準法に基づき、国土交通大臣が認定する不燃材料であり、火にさらされても20分間燃焼せず、防火上有害な変形や亀裂を防ぐ特性を持っています。
さらに、避難時に有害な煙やガスを発生させないことも要件とされています。
この不燃生地の構造には、塩ビフィルムにガラス繊維が含まれており、たとえ表面が燃えたとしても内部の繊維部分は燃え抜けることがありません。
これにより、火の粉が建物内部に侵入し、火災が拡大するのを防ぐ効果があります。
不燃生地は樹脂製の表皮とガラス基布で構成されており、火の粉を貫通させず、一定の耐火性能を維持するのが特徴です。
ただし、「完全に燃えない」のではなく、「燃え抜けない」ことがこの素材の重要なポイントとなります。
一方で、不燃生地にはデメリットも存在します。
例えば、防炎生地に比べて柔軟性が低く、折れや屈曲に弱いという特性があります。
また、コスト面でも不燃生地は高価であり、防炎生地と比較すると導入のハードルが高い点が課題です。
それでも、防火性能を重視するテント倉庫では、不燃生地の採用が火災リスク低減に寄与し、安全性を向上させる上で欠かせない要素となります。
防炎生地
防炎生地とは、火に強く、万が一着火しても燃え広がりにくい特徴を持つ生地です。
さらに、炎から離すと自己消火する特性があり、安全性の高い生地といえます。
このため、火災が発生しても延焼スピードを抑え、被害の拡大を防ぐ効果が期待されます。
特に、消防車が到着するまでの平均約8分間において、人命や物品の保護に役立つだけでなく、安全な避難経路を確保し、初期消火の時間を稼ぐ点でも重要な役割を果たします。
防炎生地はテント倉庫に限らず、雨よけテントや日除け、シートカーテン、間仕切りシートといった用途にも幅広く使用されています。
この生地は、火元が存在する限り燃焼を続けますが、火元がなくなれば自己消火する性質を持っています。
防炎品として認定されるには、日本防炎協会の品質基準を満たす必要があり、テント倉庫用の生地については、JIS A1322規格に基づく防炎2級試験の合格が求められます。
この防炎性能により、火災時の被害を抑え、倉庫の建築物や利用者に安心をもたらします。
テント倉庫の建設地域について

テント倉庫は建設地域や保管物によっても、適した生地の材質が異なってきます。
これは、防火地域や準防火地域、さらには法22条区域といった特定のエリアごとに規制が異なり、それに応じた火災被害の抑制が求められるためです。
そこで、まず建設予定地がどの地域に属するのか確認することが重要になります。
地域ごとに適切な対応が求められるため、テント倉庫を建設する予定のエリアが該当する規制区域を事前に調査しましょう。
調査方法としては、GoogleやYahoo!で「◯◯市 防火地域」や「準防火地域」といったキーワードで検索すると、基本的な情報を手軽に入手できます。
より正確な情報を得るためには、役所の都市計画課や建築指導課を訪れることが有効です。
その際、調査する場所を明確に伝えるため、住宅地図を持参するとよいでしょう。
地域ごとの規制を確認した上で、適切な建材を選定することが、安全で安心なテント倉庫の建設における重要な第一歩となります。
防火地域
防火地域は、大きく二種類に分けられます。一つは、建物が密集する都心部で、人通りや交通量が多い商業エリアに指定される場合です。
この地域では、火災による被害を最小限に抑えることが求められます。
もう一つは、災害時の延焼防止を目的とし、緊急車両が通行する幹線道路沿いに設けられる区域です。
これらの地域では、防火対策を強化するため、基本的に木造建築の建設は認められていません。
準防火地域
準防火地域は、防火地域の近隣を対象に指定される地域であり、火災の燃え広がりを抑えるための規制が設けられています。
そのため、建築物の構造には一定の基準が求められます。
例えば、地階を除いた階数が4以上、または延床面積が1500㎡を超える建築物は、耐火建築物とする必要があります。
一方で、3階建て以下かつ延床面積500㎡以下の建築物については、外壁や軒裏を防火構造とすることを条件に、木造住宅の建設が可能です。
これにより、地域の火災リスクを軽減しつつ、建築における一定の自由も確保されています。
法22条区域
防火地域や準防火地域に加え、「法22条区域」も防火規制の対象です。
これは都市計画法ではなく、建築基準法第22条に基づいて定められています。
この区域では、建築物の屋根を不燃材料で造る必要があります。
また、木造建築物などでは、延焼の危険がある外壁に防火性能の高い材料を使用しなければなりません。
地域・保管資材により異なるテント生地の条件

ここまで、テント倉庫の生地と建設地域の関係について解説してきました。
最後に、建設地域や保管物の性質によって異なる、求められる生地の材質について解説します。
条件を正しく理解し、最適なテント生地を選びましょう。
可燃性資材を保管する場合
紙やプラスチック、布製品などの可燃性資材を保管する際には、設置場所や床の広さに適したテント生地を選ぶことが重要です。
地域ごとの違いを見ていきましょう。
防火地域の場合
防火地域では、床面積に関係なく不燃生地の使用が求められます。
仮に床面積が100㎡以下であっても、延焼の恐れがなければ不燃生地が必要です。
さらに、床面積が500~1,000㎡以下の場合でも、延焼リスクがないならば不燃生地を用いることが義務付けられています。
準防火地域の場合
準防火地域では、防火条件に応じて使用できるテント生地の種類が異なります。
特に可燃性資材を保管する場合、安全性を確保するために適切な生地を選定することが重要です。
床面積が500㎡以下で延焼の危険がない場合、屋根には不燃材料を使用し、外壁には防炎性能を備えた生地が求められます。
一方、床面積が500~1,000㎡以下で延焼の危険がないケースでは、より厳しい基準が適用され、屋根・外壁ともに不燃材料を採用する必要があります。
法22条区域の場合
法22条区域において床面積1,000㎡以下で延焼の恐れがない場合、屋根には不燃材料の使用が求められ、外壁には防炎性能が必要となります。
ただし、内幕(燃え抜き防止膜)を併用する場合には、屋根材にも防炎素材を採用することが認められます。
不燃性資材を保管する場合
陶器、磁石、ガラス、金属類などの不燃性資材を保管する際には、地域ごとの違いはなく、共通した条件に従います。
床面積が1,000㎡以下であり、延焼の恐れが「ある」場合には、不燃生地を使用する必要があります。
一方、床面積が1,000㎡以下であり、延焼の恐れが「ない」場合には、防炎生地を使用する必要があります。
まとめ
テント倉庫の消防設備は、消防法に基づき適切に設置・管理することが不可欠です。
倉庫の規模や用途に応じた消火器や火災報知器の設置基準を遵守することで、火災発生時の迅速な対応が可能となります。
特に、消火器の能力単位や配置基準を正しく理解し、歩行距離の制限を考慮した適切な設置が求められます。
また、定期的な点検を怠らず、消防設備が確実に機能するよう維持することも重要です。
さらに、テント倉庫の防火対策においては、使用するテント生地の選定が火災リスクの低減に直結します。
不燃生地や防炎生地の特性を理解し、地域の規制や倉庫の用途に応じた最適な素材を選ぶことで、安全性を高めることができます。
加えて、建設地域ごとの防火規制を事前に確認し、適切な消防対策を講じることが、リスクを最小限に抑える鍵となります。
消防法の遵守だけでなく、より高度な防火対策を講じることで、火災による被害を防ぎ、安心して倉庫を運営する環境を整えましょう。
「テント倉庫」の建設をより具体的に検討したい方、お悩みをお持ちの方は、創業100周年&国内シェアNo.1のメーカー「太陽工業株式会社」までお問合わせください。長年の実績に裏打ちされた技術力と豊富な実績をもとに、最適なプランを提案させていただきます。
テント倉庫への
お問い合わせはこちら
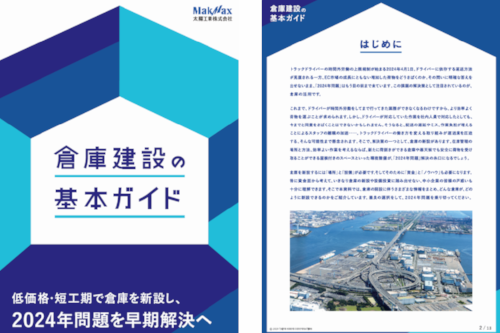
倉庫建設時に知っておくべきこと
すべて詰め込みました。
2024年問題解決の糸口
<こんな方におすすめ>
・倉庫建設で何から着手すべきかわからない
・経済的に倉庫を建設したい
・どの種類の倉庫を建設すればいいのか
・とにかく、倉庫建設の基礎知識を付けたい
・2024年問題が気になるが、 何をすればよいかわからない








