

太陽工業コラム

倉庫を建設する際は、建築基準法に基づく制限を守る必要があります。
用途地域によって建築できる場所が決まっており、どこでも自由に建てられるわけではありません。
また、建ぺい率や容積率の制限があり、建築可能な規模も決められています。
増築時も同様に規定を確認することが重要です。
本記事では、倉庫建築に関する法規制や具体的な制限について詳しく解説します。
建築基準法とは?

建築基準法は、日本で建築される全ての建物に適用される法律です。
この法律は、安全性や居住性を確保するための技術基準や規定を定めています。
特に火災時の被害を最小限に抑えるため、倉庫を含む建物には防火や避難に関する制限が設けられています。
例えば、火の広がりを防ぐ構造や、迅速な避難を可能にする設備の設置が求められます。
建築基準法における「倉庫」の定義

建築基準法において「倉庫」は特殊建築物に分類されます。
特殊建築物とは、多くの人が利用する建物を指し、学校や映画館、児童福祉施設などが該当します。
そのため、火災時の安全確保や周囲への影響を抑えるために、さまざまな制限が設けられています。
例えば、倉庫の主要構造部には一定の耐久性が求められます。特に高さや面積によって、防火性能の基準も異なります。
3階以上で、かつ面積が200㎡を超える場合、建物は耐火建築物とする必要があります。
また、総面積1,500㎡以上の倉庫には準耐火建築物の規定も適用されます。
これらの基準により、災害時の安全性を高め、利用者や周囲の人々の命を守ることが目的です。
倉庫が持つ防火性能は、利用者だけでなく周辺環境にも大きな影響を与えるため、法律により厳格に管理されています。
倉庫が建築基準法を満たすには

倉庫が建築基準法を満たすために必要な要件について、以下で詳しく解説します。
耐火要求の構造
建築基準法では、建物の用途や規模に応じた耐火性が求められます。
倉庫の場合、床面積が1,500㎡以上なら準耐火建築物とする必要があります。
また、3階以上の階で面積が200㎡を超える場合、耐火建築物にしなければなりません。
さらに、火災時の延焼を防ぐために、防火区画を一定の面積ごとに設けることが義務付けられています。これらの基準を満たすことで、安全性を高めることができます。
防火区画の設置
倉庫が建築基準法を満たすには、防火区画の設置が必要です。
防火区画の目的は、火災時に火が燃え広がることを防ぐことです。
具体的には、建築基準法施行令第112条に基づき、防火区画の基準が定められています。
防火区画の設置基準は、建物の構造やスプリンクラーの有無によって異なります。
耐火構造の倉庫では、スプリンクラーが未設置の場合、1,500㎡ごとに防火区画を設けなければいけません。
一方、スプリンクラーがある場合は3,000㎡ごとの区画設置が求められます。
防火区画を構成する壁や床は、準耐火構造とし、60分間の遮熱性能が必要です。
また、開口部には特定防火設備を設置し、同様に60分間の遮断性能を確保しなければなりません。
これらの基準を満たすことで、倉庫の防火安全性が確保されます。
内装制限
倉庫の内装は、建築基準法に基づく「内装制限」によって規制されています。
火災時の延焼を防ぎ、有害物質の発生を抑えるために、内装材の種類や使用箇所に制限が設けられています。
具体的には、高さ1.2m以上の壁や天井には、不燃材料または準不燃材料の使用が求められます。
不燃材料にはコンクリート、ガラス、金属板、モルタル、厚さ12mm以上の石膏ボードなどが含まれます。
準不燃材料には、厚さ15mm以上の木毛セメント板や、厚さ9mm以上の石膏ボードが該当します。
内装制限についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫の内装制限とは?防火材料の種類から、避けるべき違反リスクまで解説」をご覧ください。
非常用進入口の設置基準
3階建て以上の建物の場合、「非常用進入口」の設置が求められます。
これは、消防隊が迅速に建物内へ進入し、消火や救出活動を行うために必要とされるものです。
また、外壁面には屋外から進入できる開口部を設けることが義務付けられています。
具体的には、開口部の寸法は幅75cm以上、高さ1.2m以上が標準となっており、バルコニーの設置も基本要件となります。
ただし、一部例外として、規定された寸法の窓を代替進入口として使用することが可能です。
また、もし建物内に非常用エレベーターが設置されている場合には、非常用進入口の設置義務が免除される場合もあります。
建ぺい率と容積率の制限

建築基準法では、建物を無制限に建てることはできません。
地域ごとに定められた建ぺい率および容積率の範囲内での建築が求められます。
これらは敷地に対する建物の占有割合や延べ床面積の制限を定めた規則です。それぞれについて詳しく解説します。
容積率の計算方法
建ぺい率と容積率は、建物を建てる際の重要な規制です。
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積(建物が地面と接する部分の面積)の割合で、土地のどれくらいを建物が占めるかを制限します。
一方、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示すもので、建物全体のボリュームを規制する基準です。
容積率を計算する際には、延べ床面積が重要です。
延べ床面積とは、各階の床面積を合計したもので、建物全体の規模を反映します。
容積率は「容積率=延べ床面積÷敷地面積×100」の計算式で求められます。
例えば、敷地面積が120㎡で、1階90㎡・2階90㎡の建物を建てる場合、容積率は(90+90)÷120×100=150%となります。
ただし、すべての部分が延べ床面積に含まれるわけではありません。
玄関やバルコニー、ベランダ、ロフトの一部は延べ床面積から除外されます。
また、地下室やビルトイン車庫なども一定の条件下で除外される場合があります。
これにより、容積率が緩和されることがあり、この仕組みを「容積率の緩和の特例」と呼びます。
この特例は土地の有効活用に役立ちます。
たとえば、狭い敷地でも地下室を設けることで、法的制限を守りつつ床面積を確保できます。
都市計画で定められた容積率には上限がありますが、特例を活用すれば、より広い居住空間を確保できるのです。
こうした仕組みにより、規制を守りながらも効率的な土地利用が可能となります。
防災備蓄倉庫への緩和
防災備蓄倉庫に対しては一部緩和措置があります。
防災備蓄倉庫とは、非常用食料や救助物資を保管する施設です。
この倉庫には「防災倉庫」と表示し、利用者が見やすい場所に設置する必要があります。
容積率の計算では、防災備蓄倉庫の延べ床面積の1/50または1/100が除外されます。
これにより、通常の容積率制限よりも緩和された条件で建設でき、防災機能の強化が期待されます。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合を示します。
建築面積は建物を真上から見たときの面積で、階数に関係なく1階部分で計算されます。
例えば、敷地が120㎡で1フロア90㎡の2階建ての場合、建ぺい率は75%となります。
この制限は、防災や風通しの確保、街全体のゆとりを目的としています。
そのため、建築基準法により用途地域ごとに異なる建ぺい率が設定されています。
用途地域は、住宅地や商業地など13種類に分類され、それぞれ適した建ぺい率が適用されます。
特に住宅地では快適な居住環境を守るため、厳格な制限が設けられています。
忘れてはいけない用途地域の確認

都市計画法に基づく用途地域は、住みよい街づくりを目的として地域を13種類に区分する制度です。
各エリアでは、建物の用途や規模に制限があり、環境保全が図られます。
たとえば、住宅街では工場の建設が禁止され、高層マンションの高さ制限が設けられます。
一方、工業専用地域では病院の建設が認められていません。
これらのルールは「用途地域による建築物の用途制限」と呼ばれます。
用途地域についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫建築の用途地域に注意|営業倉庫と自家用倉庫でも異なる基準や選定プロセスを解説」をご覧ください。
まとめ
倉庫を建設する際は、建築基準法の各種制限を理解し、適切に対応することが重要です。
特に、用途地域によって建築可能な場所が決められており、自由に建てられるわけではありません。
また、建ぺい率や容積率の制限により、建物の規模にも制約が設けられています。
加えて、倉庫は特殊建築物に分類されるため、防火性能や避難設備の基準が厳しく設定されており、耐火建築物や防火区画の設置義務を満たす必要があります。
これらの規制は、倉庫の安全性を確保し、周辺環境との調和を図る目的で定められています。
防火対策や耐火性能、内装制限などの要件を遵守することで、災害リスクを抑えながら機能的な倉庫を実現できます。
また、用途地域の制限を事前に確認することで、建築計画のスムーズな進行が可能となります。
倉庫を建築予定の方で、建築基準法や倉庫建築について調べているが、ご不明な点やお悩みのある方がいらっしゃいましたら、ぜひ創業100周年の「太陽工業株式会社」までお問い合せください。
専門知識を活かして、法規制への対応から倉庫の建築まで、スムーズな倉庫運営をサポートいたします。
テント倉庫への
お問い合わせはこちら
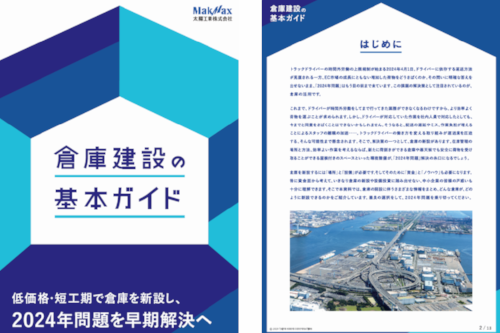
倉庫建設時に知っておくべきこと
すべて詰め込みました。
2024年問題解決の糸口
<こんな方におすすめ>
・倉庫建設で何から着手すべきかわからない
・経済的に倉庫を建設したい
・どの種類の倉庫を建設すればいいのか
・とにかく、倉庫建設の基礎知識を付けたい
・2024年問題が気になるが、 何をすればよいかわからない








