

太陽工業コラム

物流倉庫を新設する際、消防法に基づく消防設備の設置義務を理解することが重要です。
倉庫火災は大規模な被害をもたらすため、安全対策が不可欠です。適切な消火設備や避難経路の確保に加え、定期的な点検も求められます。
本記事では、必要な消防設備や法的要件、最新の防火対策のトレンドについて詳しく解説します。防災対策を強化し、安全な倉庫運営を目指しましょう。
消防法が定めた倉庫への法的義務

消防法では、大規模な倉庫や工場に対し、火災発生時の安全を確保するための消防設備の設置を義務付けています。
これは、倉庫が持つ特有のリスクに対応するための措置です。倉庫は開口部が少なく、火災発見の遅れが懸念されるほか、大量の荷物を保管する特性があります。
これらの荷物には可燃性が高いものや、有毒ガスを発生させるものも含まれるため、火災時の被害が拡大しやすくなります。
そのため、消防法では倉庫の規模や構造に応じて適切な消防設備を設置することを義務付けています。
木造倉庫は700㎡、耐火構造の倉庫は1,400㎡、内装制限のある耐火構造の倉庫は2,100㎡を超える場合、屋内消火栓設備の設置が必要です。
また、延床面積が500㎡を超える場合、自動火災報知設備の設置が求められます。
さらに、天井高が10mを超える施設では、スプリンクラー設備の設置義務が発生する可能性があります。
これらの設備を適切に整備することで、万が一火災が発生した際にも被害を最小限に抑えることができます。
また、設置した消防設備は定期的な点検と届出が求められ、適切に維持管理する必要があります。
このような法的義務を遵守することで、施設利用者や保管物の安全性が確保され、経営リスクを軽減することにつながります。
内装制限についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫の内装制限とは?防火材料の種類から、避けるべき違反リスクまで解説」をご覧ください。
倉庫に必要な消防設備

消防法では、倉庫に設置が義務付けられる設備は「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つに分類されます。詳しく解説します。
消火設備
消火設備は、火災時の初期対応に おいて 不可欠です。代表的な設備には、消火器、消火栓、スプリンクラー設備などがあります。適切な設備を設置し、維持管理を徹底しましょう。
消火器
倉庫における火災の初期段階で被害を抑えるには、消火器の設置が重要です。
設置基準としては、延べ面積150㎡以上の倉庫が対象となります。
また、地階や無窓階、3階以上の階では、面積が50㎡を超える場合に消火設備の設置が義務付けられています。
なお、無窓階とは、避難や消火活動のための開口部がない建物の地上階を指します。適切な設備を備え、火災リスクを最小限に抑えることが求められます。
スプリンクラー設備
スプリンクラー設備は、火災時に熱を自動で感知し、天井に設置されたヘッドから散水することで消火活動を行う装置です。
火災を素早く察知し、上から自動的に放水する仕組みにより、初期消火が可能となります。特にラック式倉庫においては、防災対策として有効であり、火災の拡大防止に効果を発揮します。
設置基準としては、天井の高さが10mを超え、延べ面積が700㎡以上の倉庫が該当し、加えて高層建築物では11階以上の階に設置が義務付けられています。
屋内消火栓設備
屋内消火栓設備は、消火器では対応できない火災を抑えるために設置される重要な設備です。
主に水源や加圧装置、起動装置、消火栓箱、非常電源で構成されます。消火時には、消火栓箱のホースを取り出し、伸ばして 大量の水を放射します。
設置義務は、延べ面積700㎡以上の建物や、地階・無窓階・4階以上で150㎡以上の場合に適用されます。
屋外消火栓設備
倉庫には火災対策としてさまざまな消防設備が必要ですが、その中でも屋外消火栓設備は重要な役割を果たします。
屋外消火栓設備は主に隣接する建物への延焼を防ぐ目的で設置され、特に1階および2階で発生した火災に対応して、外部からの消火活動に使用されます。
屋内消火栓設備と似た構成ながら、水圧や放水量が高く、初期火災から中期火災まで対応できる強力な消火能力を備えています。
設置基準としては、1階と2階の合計床面積が3,000㎡以上の建物が該当します。
警報設備
倉庫では火災の早期発見と周知のため、警報設備が欠かせません。いくつかの代表的な設備について解説します。
非常警報設備
非常警報設備は、火災発生を周囲に 迅速に 知らせるために不可欠な設備です。
この設備は、ボタン操作などによって警報を鳴らし、火災の発生を関係者に伝達します。
非常警報器具には、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンなどがあり、これらを用いて施設内の人々に速やかに警報を伝える役割を果たします。
特に、多数の人が利用する施設では設置が義務付けられており、収容人数が20~50人程度の施設でも非常警報器具の設置が必要です。
さらに、地階や窓のない無窓階においては、火災の発生を確実に伝えるために放送設備の設置が法的に求められます。迅速な避難を促すために、目立ちやすく、すぐに操作できる場所に配置されることが重要です。
自動火災報知機
倉庫では火災を早期に感知し、警報を発する設備が必要です。
これには熱や煙、炎を検知する自動火災報知機が含まれます。
警報はベルや音声で通知し、建物内の人々へ素早く伝えます。設置基準は延べ面積500㎡以上ですが、地階や窓のない階、3階以上では300㎡以上で義務化されます。
さらに、11階以上の階では必須となります。これにより火災被害の最小化が図られます。
火災通報装置
倉庫では火災発生時の迅速な対応が求められるため、火災通報装置を設置し、自動で消防機関に通報できるようにします。
この装置は火災が発生した際に操作することで、電話回線を利用して通報や通話が可能です。
設置基準としては、延べ面積が1,000㎡以上の倉庫が対象となりますが、一定の要件を満たせば設置が不要となる場合もあります。
漏電火災警報器
漏電火災警報器は、電気機器の漏電を検知し、火災を未然に防ぐ重要な装置です。
延べ面積1000㎡以上の施設では、設置が法律で義務付けられています。適切な設備を導入し、安全管理を徹底しましょう。
避難設備
倉庫には火災時の安全を確保するため、避難設備が必要です。ここでは代表的な設備である「誘導標識(誘導灯)」について詳しく解説します。
誘導標識(誘導灯)
万が一火災が発生してしまった際、避難経路には、非常口を示す誘導標識や誘導灯を設置して、安全な移動を確保する必要があります。
消防法の基準により、全ての建物と各階に設備を設置しなければなりません。
特に、地下階や無窓階、高層階では、避難誘導灯が必須です。
これにより、緊急時の迅速な避難を支援し、人的被害を防ぐことができます。
消防設備の最新トレンド

近年、消防設備は技術革新によって大きく進化しています。
火災対策の重要性が高まり、新たな製品が次々と登場しています。
その中でも注目されているのが、スマート消防システムの普及です。
このシステムはIoT技術を活用し、センサーやカメラがネットワークで連携します。
リアルタイム監視が可能となり、火災発生時には即座に通知されます。
これにより、火災を早期発見し、迅速な対応で被害を最小限に抑えられます。
また、ドローンの活用も進んでいます。
高層ビルや広範囲の監視が必要な現場で、その有用性が認識されています。
赤外線カメラや熱感知センサーを搭載したドローンは、火災の発生場所や進行状況を素早く特定できます。
これにより、消防隊の安全を確保しながら、効果的な消火活動を支援します。
さらに、消火用ロボットの進化も重要なポイントです。
これらのロボットは、危険な場所に進入し、消火活動を行うことが可能です。
特に化学工場や原子力発電所など、高リスク環境での活躍が期待されています。
自動制御技術や高度なセンサーを備え、正確かつ効率的な対応が可能です。
消防設備の定期点検

消防設備は設置後も継続的な管理が必要であり、消防法に基づいて定期点検が義務付けられています。
点検は半年に1度の機器点検と、1年に1度の総合点検に分かれています。
機器点検では、設備の損傷や変形の有無を確認し、総合点検では設備を実際に動作させて状態を確認します。
点検結果は維持台帳に記録し、管理に活用します。
記録の提出義務はありませんが、適切な管理が重要です。また、それぞれの点検で確認すべき内容は設備によって異なります。
機器点検(半年に1回)
消防設備の定期点検の一環として、半年に一度実施される機器点検は重要です。
これは火災時に適切に作動するかを確認するためのもので、外観や設置場所の確認に加え、各機器の操作による詳細な点検を行います。
消火器の点検では、本体の損傷や表示・標識の状態を慎重に確認します。
また、設置位置が適切かを目視や簡易的な測定で調査し、指示圧力値が基準範囲内にあることを確認します。
屋内消火栓設備では、貯水槽や給水装置、水位計、バルブ類に損傷や変形がないかを入念にチェックします。
さらに、配管やノズルの状態も確認し、正常に使用できるかを検査します。
スプリンクラー設備の場合、ヘッド部分に損傷や障害物がないかを確認し、感知器の動作や加圧送水装置の起動状況も検査します。
これらの点検を実施することで、万一の火災時に適切に作動し、安全性を確保できます。
総合点検(1年に1回)
消防設備の総合点検は、年に一度実施される点検です。
設備が適切に機能するかを確認するために、実際に作動させる形で実施されます。
点検内容は設備ごとに異なります。
例えば屋内消火栓設備では、加圧送水装置の動作を確認して、放水量や放水圧力が基準を満たしているかをチェックします。
スプリンクラー設備も同様に、装置が適切に作動し、放水性能が規定の範囲内であるかどうかを点検します。
漏電火災警報機については、正常に作動し、作動電流値が+10%から-60%の範囲内であるかを確認します。
非常警報器では、ベルやサイレンの音圧が90dB以上であること、加えて火災警報表示や音響装置、スピーカーも問題なく鳴動するかを点検します。
これらの総合点検は、消防設備が緊急時に確実に機能し、人命や財産を守るために必要不可欠な手続きです。
3年に1度の報告義務
消防法第17条に基づき、「非特定防火対象物」に分類される倉庫は、消防設備の点検結果を3年に1度、消防庁または消防署長に報告する義務があります。
この点検の対象には、消火器、火災報知器、避難誘導設備などが含まれ、適正な機能を維持するために法令に則ったメンテナンスが求められます。
万が一、報告義務を怠った場合、消防法第44条により30万円以下の罰金または拘留が科せられる可能性があります。
また、法令遵守の責任を果たさないことは、業務上の信頼性低下や重大な損害につながるリスクも伴います。
適切な管理を徹底し、法的義務を守ることが重要です。
倉庫における消防法の注意ポイント

これまでお伝えしてきた内容以外にも、注意すべきことがあります、3つの注意ポイントを解説します。
危険物倉庫に対する厳格な規定
倉庫や工場には様々な種類がありますが、特に危険物を扱う施設では火災対策が非常に重要です。
そのため、危険物倉庫においては、建築規模や構造、設備に関してより厳格な規定が定められています。
例えば、床面積は1,000㎡以下とすることが義務付けられ、壁は耐火構造としなければなりません。
さらに、指定数量が10倍以上となる場合には、避雷設備の設置が必要です。
加えて、立地条件や保管可能な危険物の種類についても細かい規制があります。
したがって、危険物倉庫の建築を計画する際には、これらの規定を十分に考慮し、適切な対応を行うことが不可欠です。
有資格者による点検が求められる場合
消防法施行令第36条第2項では、特定の要件を満たす建物に対して、有資格者による点検を義務付けています。
倉庫のような「非特定防火対象物」の場合、延べ面積が1,000㎡以上であれば、この点検の対象となります。
非特定防火対象物とは、特定の利用者に限定されない建物のことを指します。
点検を行う有資格者には、消防設備士または消防設備点検資格者が該当します。
一方、延べ面積が1,000㎡未満の建物であれば、資格を持たない人が自ら点検を実施することも可能であり、防火管理者などに依頼することも認められています。
ただし、点検の内容は建物の規模や種類によって異なるため、適切な判断が重要です。
50人以上の従業員がいる場合に必要な防火管理者
消防法施行令により、50人以上の従業者がいる倉庫では、防火管理者を置くことが義務付けられています。
従業員数をもとに収容人員を算出し、それに基づいた具体的な基準が設けられています。
防火管理者は火災予防のために重要な役割を担い、消防計画の作成と届け出、訓練の実施、設備の点検・整備を行う必要があります。
これらを適切に実施することで、災害時の被害を最小限に抑え、倉庫の安全を確保できます。
まとめ
倉庫における消防法の遵守は、安全な運営のために欠かせません。
倉庫はその構造上、火災発生時に被害が拡大しやすいため、適切な消防設備の設置と維持管理が求められます。
消火器やスプリンクラー、火災報知器といった基本的な設備に加え、施設の規模や構造に応じた設備基準を理解し、適切に対応することが重要です。
また、定期点検や有資格者による確認を通じて、常に設備の機能を維持し、消防法の報告義務を果たすことで、法的リスクの回避にもつながります。
近年では、IoTを活用したスマート消防システムやドローンによる監視など、最新技術を取り入れることで防火対策の精度が向上しています。
倉庫の防災対策を強化し、法令を遵守することで、従業員や保管物の安全を守るとともに、事業の安定運営を実現しましょう。
また、倉庫の建築方法の選択も、安全かつ効率的な運営を行う上で重要なポイントです。
多くの企業が「テント倉庫」の導入を進めています。
テント倉庫とは、鉄骨を組み立ててシート膜を張った建築物で、低コストかつ短工期で建築が可能です。
耐久性や耐候性にも優れており、日中は照明が不要なほど明るいため、作業効率が向上します。
先進的なメーカーや物流業界では、多数の企業がテント倉庫を導入しています。
効率的な倉庫運営を実現するための手段として、テント倉庫を検討してみてはいかがでしょうか。
「テント倉庫」に興味を持たれた方は、ぜひ一度、創業100周年&国内シェアNo.1のメーカー「太陽工業株式会社」までお問合わせください。
テント倉庫への
お問い合わせはこちら
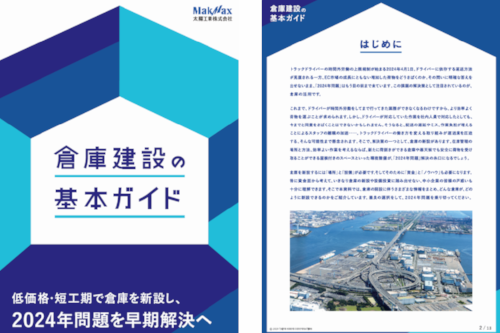
倉庫建設時に知っておくべきこと
すべて詰め込みました。
2024年問題解決の糸口
<こんな方におすすめ>
・倉庫建設で何から着手すべきかわからない
・経済的に倉庫を建設したい
・どの種類の倉庫を建設すればいいのか
・とにかく、倉庫建設の基礎知識を付けたい
・2024年問題が気になるが、 何をすればよいかわからない








