

太陽工業コラム

日本の建物では、火災被害を防ぐためにさまざまな工夫がされています。
その一つが、建築基準法で定められた「内装制限」です。
これは、不燃材料を使用すべき部分や、木材を使える条件などを規定するものです。
倉庫でも、このルールを守ることが求められます。
本記事では、防火材料の種類や違反リスクについて詳しく解説します。
安全な倉庫運営のために、ぜひ参考にしてください。
倉庫の内装制限とは?

倉庫の内装制限とは、火災発生時に有害物質の発生や避難の妨げを防ぐため、内装材の材質や使用箇所に規定を設けることです。
これは、建築物や施設が安全かつ快適に使用できるよう定めた「建築基準法」の一部です。特に、避難経路の安全確保や延焼防止が重視されています。
建築基準法についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫に適用される「建築基準法」とは?必要な要件から、建ぺい率や容積率の制限まで解説」をご覧ください。
倉庫も一定の条件を満たす場合、内装制限の対象になります。
例えば、壁や天井が1.2m以上の高さになる場合、建物が耐火建築物か準耐火建築物かによって規制が異なります。
一方、スプリンクラーや自動式消火設備、排煙設備が設置されている倉庫では、場合によっては制限が緩和されることもあります。
倉庫の内装工事では、防火対策として不燃または準不燃材料の使用が求められます。
これらの材料は、防火材料としての基準を満たし、防災基準にも適合している必要があります。
適切な対策を講じることで、安全で機能的な倉庫環境を整えることが可能です。
防火材料の種類
倉庫の内装制限では、防火材料の使用が求められます。
防火材料の要件は建築基準法施行令第108条の2に基づき、燃焼しないこと、変形や溶融など防火上有害な損傷が起きないこと、さらに避難に有害な煙やガスを発生させないことが必要です。
これらの条件を満たす材料が防火材料とされ、加熱時の耐久時間によって3つの区分に分類されます。
それぞれの特性を理解し、適切に使用することが重要です。それぞれについて詳しく解説します。
不燃材料:建設省告示第1400号(国土交通省告示第1178号改正)
不燃材料とは、無機質または金属質の素材で構成され、燃えにくい特性をもつ建材のことです。
日本では、建設省告示第1400号および改正後の国土交通省告示第1178号により、不燃材料の種類が規定されています。
代表的な不燃材料には、コンクリート、瓦、れんが、繊維強化セメント板、陶磁器質タイルなどがあります。
また、厚さが規定されているものとして、3mm以上のガラス繊維混入セメント板や12mm以上の石膏ボードが含まれます。
これらは防火性能だけでなく、耐久性や断熱性にも優れています。
さらに、国土交通大臣の認定を受けた製品には「NM-〇〇〇〇」という形式の認定番号が付与されます。
認定製品を使用することで、安全性を確保し、建築基準法の要件を満たすことが可能となります。
倉庫の内装計画では、これらの不燃材料を適切に採用し、火災対策を徹底することが求められます。
準不燃材料:建設省告示第1401号
準不燃材料の基準は、建設省告示第1401号(平成12年5月30日)によって定められています。
この基準では、火災時に通常の火熱が加わった場合、20分間にわたり「令第108条の2」に基づく性能要件を満たす必要があります。
国土交通大臣が認定した準不燃材料には、「QMー〇〇〇〇(四桁数字)」の認定番号が付与されます。これにより、基準を満たしていることが確認できます。
代表的な準不燃材料には、以下のものがあります。 倉庫内でこれらの材料を適用することで、火災時の被害を抑えることができます。
● 9mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)
● 厚さ15mm以上の木毛セメント板
● 厚さ9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重0.9以上)
● 厚さ30mm以上の木片セメント板(かさ比重0.5以上)
● 厚さ6mm以上のパルプセメント板
難燃材料:建設省告示第1402号
倉庫の内装制限には該当しませんが、防火材料の一種として「難燃材料」があります。
これは、建設省告示第1402号(平成12年5月30日)に基づいて定められた材料です。
難燃材料は「準不燃材料」として認められることが必要です。
これにより、火災時でも一定時間性能を維持することが求められます。
具体的には、加熱開始後10分間に建築基準法施行令第108条の2で定められた耐火性能を満たさなければなりません。
また、難燃合板は厚さ5.5mm以上、石膏ボードは厚さ7mm以上で、ボード用原紙の厚さは0.5mm以下であることが求められています。
これらの基準を満たすことで、防火性能を確保することが可能となります。
内装制限の違反リスク

建築基準法に基づく内装制限を守らないと、建物が法的基準を満たさず、安全性が損なわれます。
特に、火災時の被害拡大リスクが高まり、従業員や利用者の安全が脅かされる可能性があります。
また、法令違反となれば、行政指導が入ります。まず、是正勧告が出され、一定期間内に改修が求められます。
対応が遅れると命令に進み、悪質な場合は使用停止となるおそれがあります。
最悪の場合、建物の除去命令が下され、取り壊しが必要になることもあります。
さらに、故意に基準に違反すると、個人には懲役3年以下あるいは罰金300万円以下、法人には最大1億円以下の罰金が科せられます。
こうしたリスクを避けるためにも、内装制限を遵守することが重要です。
防止策
内装制限や建築制限は専門的知識が求められるため、素人が正確に判断するのは困難です。
適切な対応を取るために、施工業者や自治体の建築課、または消防署に事前相談を行いましょう。
特に、消防署では「事前相談制度」を提供しており、防火対策の適切性を確認できます。
さらに、自治体の建築課に相談することで、用途地域や関連法規との整合性を確かめることができます。
施工業者の選定も重要です。
法令に詳しく、過去に違反歴のない業者を選ぶことで、適切な施工が期待できます。
また、施工時には設計通りに工事が進んでいるか、第三者機関や建築士の現場確認を依頼すると、品質管理が徹底できます。
完成後も、法改正への対応や定期点検を行い、安全性を維持することが求められます。
適切な対策を実施することで、法律違反を防ぎ、安心で安全な建物環境を維持できます。
内装制限で注意するべき「木材」の取り付け方

木材は燃えやすい性質を持つため、内装に使用する際には慎重な対応が求められます。
特に倉庫など内装制限がある建物では、不燃材や準不燃材料を基本とし、基準を満たした木材でなければ使用できません。
世界的な建築物の木質化推進に伴い、日本でも建築基準法が緩和され、燃えにくい木材の選択肢が増えています。
その結果、内装制限がある倉庫でも、コストを抑えた木造倉庫の普及が進んでいます。
木材を内装材として使用する際には、いくつかの条件を確認する必要があります。
一つ目は、木材の厚みに応じて適切な下地に取り付けられているかどうかの確認です。
下地が不十分な場合、火災時に木材が崩れるリスクが高まります。
二つ目は、天井の仕上げが不燃または準不燃材料で構成されているかどうかの確認です。
特に火の回りやすい天井部分は、防火性能が重要になります。
三つ目は、木材表面に燃焼を助長する溝がないかどうかの確認です。
溝があると、火が燃え広がる速度が早まるため、適切な処理が求められます。
内装制限を遵守することで、安全な施工が可能となります。
ただし、建築を行う地域によっては、自治体独自の条例が存在することもあるため、事前に詳細を確認することが不可欠です。
技術の進化により、燃えにくい木材が増え、木材の利用可能性がさらに拡大しています。
その流れの中で、鉄骨造倉庫と比較して経済的な木造倉庫が、新たな選択肢として注目を集めています。
木造倉庫のメリット
木材は燃えやすいため、内装制限に従った取り付けが求められます。
特に、防火性能を確保するために、不燃処理や適切な仕上げが必要です。
一方で、木造倉庫には多くのメリットがあります。
まず、建設期間が短く、コストを抑えやすい点が挙げられます。
木材は鉄骨よりも軽量なため、基礎工事の規模を小さくできます。
さらに、一般住宅と共通の資材を使用でき、調達が容易です。
技術の進歩により、大規模な倉庫の建設も可能になっています。
倉庫に関連するその他の法律

倉庫の建設には、複数の法律を遵守する必要があります。
まず、建築制限では、倉庫が耐火建築物であるため、規模に応じた構造上の制限があります。
たとえば、一定の面積ごとに防火区画を設け、非常口には特定防火設備を設置する必要があります。
さらに、用途制限では、倉庫を建設できる区域が都市計画法で定められており、特に住宅区域では、基本的に倉庫の建設が禁止されています。
用途地域についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫建築の用途地域に注意|営業倉庫と自家用倉庫でも異なる基準や選定プロセスを解説」をご覧ください。
まとめ
倉庫の内装制限は、建築基準法で定められた防火対策の一環として、不燃材料や準不燃材料の使用を求めるものです。
違反が発覚すれば行政からの是正指導や使用停止命令、さらには罰金など大きなリスクが伴います。
こうした厳格な制限の背景には、倉庫の安全確保と法令違反の回避が大前提としてあるため、施工業者や自治体への事前相談、さらに消防署での確認が欠かせません。
一方で、コストや工期に配慮しつつ、安全性も確保したいと考える企業が増えているのも現状です。その際に注目される選択肢が「テント倉庫」です。
テント倉庫とは、鉄骨を組み立ててシート膜を張った建築物で、低コストかつ短工期で建築が可能です。
耐久性や耐候性にも優れており、日中は照明が不要なほど明るいため、作業効率が向上します。
先進的なメーカーや物流業界では、多数の企業がテント倉庫を導入しています。効率的な倉庫運営を実現するための手段として、テント倉庫を検討してみてはいかがでしょうか。
「テント倉庫」に興味を持たれた方は、ぜひ一度、創業100周年&国内シェアNo.1のメーカー「太陽工業株式会社」までお問合わせください。
テント倉庫への
お問い合わせはこちら
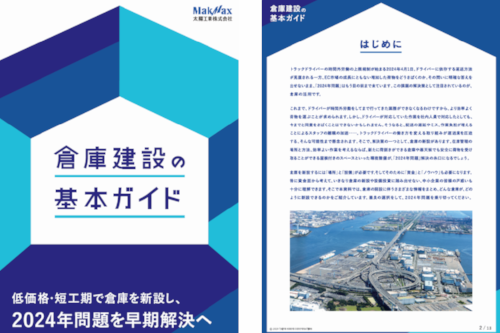
倉庫建設時に知っておくべきこと
すべて詰め込みました。
2024年問題解決の糸口
<こんな方におすすめ>
・倉庫建設で何から着手すべきかわからない
・経済的に倉庫を建設したい
・どの種類の倉庫を建設すればいいのか
・とにかく、倉庫建設の基礎知識を付けたい
・2024年問題が気になるが、 何をすればよいかわからない








