

太陽工業コラム

倉庫を建築する際は、「用途地域」の確認が欠かせません。
用途地域とは、国土交通省が土地の利用目的を定めた分類です。
これにより倉庫の建築が可能か、また適用される制限が決まります。
特に営業倉庫と自家用倉庫では異なる基準があるため、詳しい選定プロセスを理解することが必要です。
本記事では、それぞれの基準や選定のポイントについて詳しく解説します。
用途地域とは?

用途地域とは、国土交通省が都市計画に基づいて土地の利用目的を定めた地域です。
特に市街化区域では指定が義務付けられ、計画的な土地利用が促されています。
これにより、地域ごとに建築可能な建物の種類や規模が規制されます。
用途地域は「工業系」「商業系」「住宅系」の3つに大別され、さらに13区分に分かれます。
住宅系には「第一種低層住居専用地域」などがあり、商業系には「近隣商業地域」などが含まれます。
工業系には「準工業地域」などが指定され、地域ごとに適した利用が定められています。
この制度により、無秩序な開発が防がれ、住環境や事業活動の適切なバランスが保たれます。
企業や個人が土地を活用する際には、用途地域の確認が不可欠です。
工業系の用途地域
工業系の用途地域は、主に工場や倉庫を建てるためのエリアです。
住宅や商業施設の混在を制限し、産業活動が円滑に行われるように設計されています。
| 地域名 | 規制内容 | 建築可能な建物 |
| 準工業地域 | 住宅や小規模工場が共存可能 | 住宅、工場、店舗、倉庫 |
| 工業地域 | 住宅の建築も可能だが、工場が中心 | 工場、倉庫、店舗、一部の住宅 |
| 工業専用地域 | 工業用途に限定され、住宅・学校などは禁止 | 工場、倉庫 |
商業系の用途地域
商業系の用途地域は、主に店舗や事務所、商業施設の建設を目的とした地域です。
これは「近隣商業地域」と「商業地域」の2種類に分類され、それぞれ建築可能な建物や規制内容が異なります。
近隣商業地域は「商店街」や県道、国道といった「幹線道路沿い」に指定されるケースが多く、住環境に配慮した建築が求められます。
一方、商業地域は「大都市」や「ターミナル駅」の周辺に指定されるケースが多く、より大規模な商業施設が建設可能です。
| 地域名 | 規制内容 | 建築可能な建物 |
| 近隣商業地域 | 近隣住民の利便性を高めるための商業活動を許容 | 店舗、事務所、カラオケボックス |
| 商業地域 | 近隣商業地域よりも、より商業に特化 | オフィスビル、映画館、百貨店 |
住宅系の用途地域
住宅系の用途地域は、主に人々の居住空間を形成するために計画的に指定された土地のことです。
建築できる建物の種類は、地域ごとの規制によって異なります。住宅を中心とし、規制が厳しい地域から比較的緩やかな地域まで、以下の8つに分類されます。
| 地域名 | 規制内容 | 建築可能な建物 |
| 第一種低層住居専用地域 | 高さ制限が厳しく、低層住宅を中心とする | 戸建住宅、小規模アパート、小学校など |
| 第二種低層住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域に加え、小規模店舗が可能 | 戸建住宅、小規模アパート、店舗(一定規模以下)など |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅向けの地域で、病院や大学も可能 | アパート、マンション、病院、大学など |
| 第二種中高層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域よりも店舗や事務所の制限が緩和 | マンション、病院、大学、一定規模の店舗など |
| 第一種住居地域 | 住居を主としつつ、小規模な商業施設も可能 | マンション、店舗、学校、病院など |
| 第二種住居地域 | 第一種住居地域よりもさらに商業施設が許容される | マンション、商業施設、ホテル、事務所など |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いなどで、住居と商業施設の共存を図る | 住宅、ショッピングセンター、一定規模の工場など |
| 田園住居地域 | 農業と住居が共存できる地域 | 住宅、農産物直売所、農家レストランなど |
倉庫を建設できる用途地域

用途地域は3種類13分類に分かれており、それぞれ建設可能な施設が異なります。
倉庫も用途地域の規制を受けるため、建設できる場所が制限されています。
倉庫には、営業を目的とする「営業倉庫」と、個人利用の「自家用倉庫」の2種類があり、用途地域によって建設できる地域が異なります。
つまり、事業用途の倉庫と個人用途の倉庫で適した地域が異なる仕組みとなっています。
このため、倉庫を新たに建設する際には、利用目的に応じた適切な用途地域を確認する必要があります。
営業倉庫を建築可能な用途地域
営業倉庫を建築できる用途地域は6つあります。
準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域です。
住居系地域では厳しい制限が課されており、営業倉庫を建てられるのは準住居地域のみとなっています。
一方で、商業系や工業系の地域では用途地域による制限がなく、建築が認められています。
営業倉庫は大規模な設備と人の出入りを伴うため、住環境への影響が大きく、住居系地域での規制が強化されています。
自家用倉庫を建築可能な用途地域
倉庫を建設できる用途地域は10種類あります。
そのうち7種類の第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域では、用途地域の制限なく建設が可能です。
一方、第二種中高層住居専用地域では2階以下かつ1,500㎡以下、第一種住居地域では3,000㎡以下の条件付きで建設が認められます。
田園住居地域では、農産物や農業資材を貯蔵する目的でのみ建設ができます。
倉庫には工業系の用途地域がオススメ

倉庫を利用する際は、工業系の用途地域にある施設を選ぶのがおすすめです。
工業系地域では、建物の階数や広さ、保管物に関する法規制が少なく、柔軟な運用が可能です。
特に、大量の危険物を保管する場合は、こうした地域が適しています。
また、工業系地域の多くは高速道路や幹線道路が近く、物流の利便性も高いです。
交通アクセスが良いことで、配送の効率化やコスト削減にもつながります。
さらに、倉庫のスペース確保や保管物の自由度が高いため、事業の成長にも対応しやすくなります。
ただし、取り扱う商品の特性によっては、商業系や住宅系の地域と組み合わせた運用が必要な場合もあります。
用途に応じた柔軟な地域選びが重要です。
建ぺい率と容積率による建築制限に注意

建物が建築可能な地域であっても、無制限に建てられるわけではありません。
各地域には建ぺい率と容積率が定められており、それに基づいて建築の制約が課せられています。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は延床面積の割合を指し、これらの基準によって建築計画が制限されるため、十分な理解が必要です。
容積率とは
建ぺい率と容積率は、土地に建築できる建物の規模を制限する重要な基準です。
建ぺい率は、敷地面積に対する建物の建築面積の割合です。
一方、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を指します。
延べ床面積とは、建物内のすべての階の床面積を合計したものです。
容積率は、「延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100」という計算式で求められます。
たとえば、敷地面積が100㎡の土地に70㎡のフロアを2階建てで建てた場合、容積率は「(70+70)÷100=140%」となります。
すべてのフロアが計算対象となりますが、玄関やバルコニー、ロフトなど一部の構造は延べ床面積に含まれません。
また、地下室やガレージは容積率から除外される場合があります。
これは「容積率の緩和の特例」と呼ばれ、都市計画によって容積率の上限が緩和される制度です。
この制度を活用することで、敷地が狭い場合でも有効に土地を活用できます。
建築計画を立てる際は、これらの制限や特例を十分に考慮し、適切な設計を行うことが求められます。
防災備蓄倉庫における緩和措置
防災備蓄倉庫とは、災害時に備え、非常用の食料や救助物資を保管する施設です。
利用者が認識しやすいよう、外部から見える場所に「防災倉庫」と明記する必要があります。
この倉庫を設ける場合、容積率の一部が免除されます。
具体的には、延べ床面積の1/50を算出時に除外することが可能です。
また、防災目的で設置する場合は、延べ床面積の1/100まで容積率免除が適用されます。
これにより、より有効なスペース設計が可能になり、防災対策の強化が期待できます。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指します。
建築面積は建物を真上から見たときの面積で、階数に関係なく1階部分の広さで計算されます。
例えば、100㎡の土地に、1フロア50㎡の建物を建てた場合、建ぺい率は50%になります。
同じ広さの敷地に75㎡の建物を建てた場合、建ぺい率は75%となります。
この制限は、防災や風通しを確保するために設けられています。
建ぺい率の上限は建築基準法によって定められ、地域ごとに異なります。
これらの違いは「用途地域」と関係しており、13種類の用途地域ごとに異なる建ぺい率が設定されています。
それぞれの地域に適した建築基準を設定することで、安全性や快適性を維持しています。
建築基準法についてより詳しい情報を知りたい方は、記事「倉庫に適用される「建築基準法」とは?必要な要件から、建ぺい率や容積率の制限まで解説」をご覧ください。
用途地域の選定プロセス

工場や倉庫を建設する際、最初に確認すべきは対象地の用途地域です。
用途地域を調べるためには、自治体が提供する都市計画図やオンラインツールを活用します。
多くの自治体では窓口や公式ウェブサイトで情報を公開しており、東京都の場合は「都市計画情報等インターネット提供サービス」を利用できます。
また、全国の都市計画図をまとめたサイトや、国土交通省の「全国都市計画 GISビューア」も活用可能です。
ただし、最も信頼できる情報は自治体の公式データであるため、常に最新情報を確認することが重要です。
次に、用途地域ごとの規制内容を調べる必要があります。
主な規制として、建築可能な用途や構造物の規模に関する基準が設けられています。
例えば、建ぺい率や容積率、高さ制限などがあり、これらを考慮しなければ計画が大きく変更される可能性があります。
こうした規制の解釈には専門的な知識が必要となるため、専門家に相談することが推奨されます。土地の用途地域を正確に把握し、適用される法規を適切に理解することで、スムーズに建設を進めることができるでしょう。
まとめ
倉庫を建設する際には、まず用途地域の確認が不可欠です。
用途地域は都市計画に基づいて定められており、地域ごとに建築可能な施設が異なります。
特に営業倉庫と自家用倉庫では適用される基準が異なるため、事前に十分な調査が必要です。
営業倉庫は商業系や工業系の地域での建設が認められる一方で、住居系地域では厳しい制限があるため注意が求められます。
一方、自家用倉庫は比較的多くの用途地域で建設可能ですが、規模や用途に応じた制限が設けられています。
また、建築可能な地域であっても、建ぺい率や容積率といった法規制により、建物の規模や設計に制約が生じることも考慮しなければなりません。
これらの制限を適切に理解し、地域ごとの規制を踏まえた計画を立てることで、より効率的かつ適法な倉庫建設が可能となります。
用途地域の確認は自治体の都市計画図やオンラインツールを活用し、必要に応じて専門家の助言を得ながら慎重に進めることが重要です。
用途地域の確認が済み、実際に倉庫の建築計画を進めている方にとっては、建築方法の選定も重要なポイントとなります。
倉庫の種類や用途によっては、一般的な鉄筋コンクリート造や鉄骨造だけでなく、「テント倉庫」という選択肢も検討する価値があります。
テント倉庫とは、鉄骨を組み立ててシート膜を張った建築物で、低コストかつ短工期で建築が可能です。
耐久性や耐候性にも優れており、日中は照明が不要なほど明るいため、作業効率が向上します。
先進的なメーカーや物流業界では、多数の企業がテント倉庫を導入しています。効率的な倉庫運営を実現するための手段として、テント倉庫を検討してみてはいかがでしょうか。
「テント倉庫」に興味を持たれた方は、ぜひ一度、創業100周年&国内シェアNo.1のメーカー「太陽工業株式会社」までお問合わせください。
テント倉庫への
お問い合わせはこちら
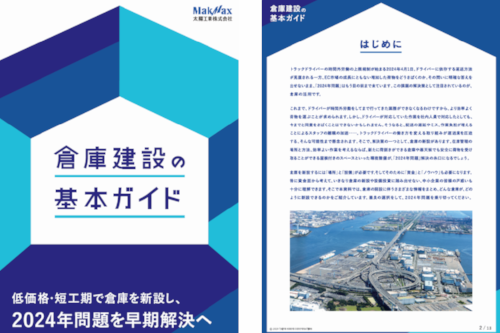
倉庫建設時に知っておくべきこと
すべて詰め込みました。
2024年問題解決の糸口
<こんな方におすすめ>
・倉庫建設で何から着手すべきかわからない
・経済的に倉庫を建設したい
・どの種類の倉庫を建設すればいいのか
・とにかく、倉庫建設の基礎知識を付けたい
・2024年問題が気になるが、 何をすればよいかわからない








