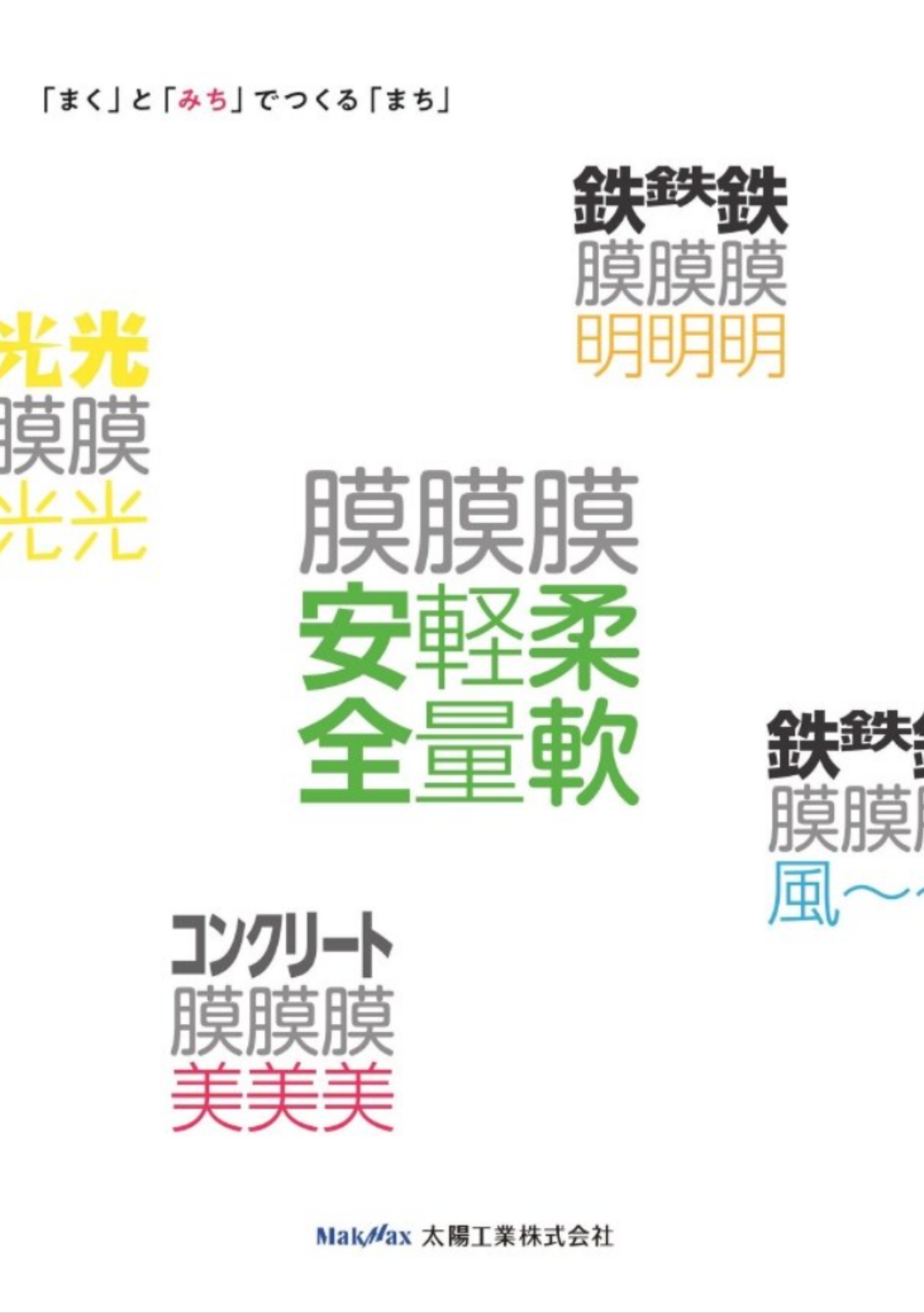橋梁ラッピング
橋梁の美装と長寿命化で、都市の新しい景観を創ります。
薄暗く寂しいイメージのガード下も、巨大な構造物を膜材で包むことで、スッキリした心地よい雰囲気の空間に変わります。また、汚れにつよく白さを保つ膜材は、光の反射率が高く(可視光反射室約77%)、桁下空間全体を明るくします。(NETIS:KK-130051-A 膜式橋梁外装工法)
製品・サービス紹介
特長
「薄暗い・寂しい」イメージから、居心地のよい場所へ。
「高架橋をどかせる訳にもいかないしね。でも、夜は人通りが少ないので、子どもたちに行かないように言っています。」
いつもの風景になっている高架橋ですが、空を覆ってしまうほどの大きさと圧迫感は、街の景観だけでなく、周辺で暮らす人たちにも少なからず心理的な影響を与えています。橋脚部分の汚れや老朽化。大きな金属がむき出しになった構造部分や、鳩の糞害などによる汚れなど。そのような無機質で暗いイメージをもった橋梁を膜材でカバーして、心地よい雰囲気に変えることができれば、どのような変化が起こるでしょうか。
美しいデザインによる景観の変化。明るい空間づくりによって人の同線が変わり桁下空間の用途が変わる。それは街全体の印象にも波及していくことになります。
そんな課題を解決するための新しい橋梁外装工法が、膜で橋桁部分を包むというアイデア。
従来の金属素材とは異なって、膜材(布)がつくり出すやわらかな曲面の美しいフォルムは、橋梁の印象をがらりと変えるとともに、コミュニティの場を創出するなど町の新たな可能性を拡げます。
膜材ならではの自由な形状が、デザイン性という楽しさをプラス。
世界のスタジアムや東京ドームなどのスポーツ施設。万博会場のパビリオンなどのイベント施設、ショッピングモールなどの商業施設。さらに、駅のインフラ整備など。
さまざまなシーンで採用されている膜素材は、他の建材にはないデザイン性を実現しています。
軽くてやわらかい膜材は、柱が少なく大スパンで自由な形状をつくり出せ、3次元的な曲面デザインが特長。それは大規模な橋梁デザインにも応用することができます。
都市インフラのデザインは、そこで暮らす人々に大きな心理的影響を与えるもの。「高架橋は無機質なもの」という固定概念をくつがえす、新たなデザインの拡がりを秘めています。
ライトアップ効果でさらに美しい風景を。
膜材をつかった建築が世界各地に存在するなか、いま注目されているのが、膜と照明のコラボレーション。光をやわらかく透過する膜材の特性をいかして、都市インフラや対象のビルが新たな存在感を得ています。
膜材ならではの柔らかなフォルムと質感。そこから照らし出される光や映像は、平面では表現できない陰影を生み出し、さらに幻想的な世界をつくり出します。また、広告や実用的な情報を投影することもできます。